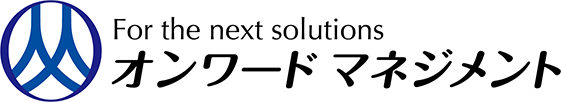福利厚生制度 退職金制度のすすめ

退職金制度は強力な福利厚生制度
「うちは最低限の福利厚生制度が整っているから十分だよ」、という考えはもう時代遅れかもしれません。近年、法定以上の充実した福利厚生制度を導入する企業が増加しています。
就職活動において「充実した福利厚生制度」は常に上位にランクインしており、求職者にとって就職先を決定する際に重要な決め手となっています。企業の先進的な福利厚生制度は、企業の社会的責任を果たす姿勢を示し、ブランド価値や信頼性の向上にも寄与します。
退職金制度の構築について
従業員の将来に対する安心感を提供し、企業への信頼を高めるための退職金制度。しかし複雑さや債務化する懸念が先立ち、導入を躊躇する企業様が多いかと思います。しかし、情報を集めると、企業型確定拠出年金(企業型DC)は複雑な確定給付型年金と異なり、中小企業にとって比較的導入しやすい制度です。
退職金 資金準備制度
| 中小企業退職金共済 | 民間保険 | 確定拠出年金 (企業型401k) |
確定給付企業年金 (DB) |
|
|---|---|---|---|---|
| 加入要件 | あり | ない | ない | ない |
| 退職給付債務 | 発生しない | 発生する | 発生しない | 発生する場合あり |
| 損金性 | あり | 一部あり | あり | あり |
| 運用リスク | 負わない | 負わない | 社員が負う | 会社が負う |
| 運営経費 | 低い | 低い | 低い(総合型) | 低い(基金型) |
| 借り入れ | 不可 | 可 | 不可 | 不可 |
| 経営者加入 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
| 掛金上限額 | 30,000円 | なし | 55,000円 | なし |
| その他 | 1年間の掛金の助成あり | 会社が解約返戻金を受取り、会社から社員に支給 | 投資教育が必要 60歳まで受給できない |
制度の縛りが少なく、会社にあった制度にしやすい |
確定拠出年金(企業型DC)と確定給付企業年金(DB)の違い
| 確定拠出年金(企業型DC/401k) | 確定給付企業年金(DB) | |
|---|---|---|
| 運用リスク | 社員が負う | 会社が負う |
| 運用が不調となった場合 | 将来の給付額が減る | 原則将来の給付額は減らない 会社が追加の掛金を負担する |
| 掛金上限額 | 55,000円/月 (企業年金制度あり:27,500円) |
なし |
| 受給時期 | 原則60歳まで受給できない | 退職時または将来年金で受給するか選択が可能 |
| 投資教育 | 必要あり | 必要なし |
また、その他にも数々のメリットが享受できます。
確定拠出年金(企業型DC)のメリット
-
- 企業の財務負担が軽減
- 確定拠出年金は、企業が拠出する金額があらかじめ定められているため、将来の支払い負担が予測しやすくなります。確定給付型年金と異なり、退職時の支払い額が変動しないため、企業の財務負担を軽減します。
-
- 負債として計上されない
- 確定拠出年金は、企業のバランスシートに負債として計上されません。これにより、企業の財務状況を悪化させることなく、従業員の福利厚生を充実させることができます。
-
- リスク管理が容易
- 確定拠出年金では、運用リスクは従業員が負うため、企業は市場の変動リスクを負う必要がありません。これにより、経済状況の変動に対する対応が柔軟に行えます。
元々当社では中小企業退職金共済と生命保険を利用して従業員退職金相当額を準備してきましたが、その一部を企業型確定拠出型年金(401K)の拠出にあてる選択をしました。このことで、拠出された掛け金は全額損金扱いとなりますし、従業員にとっても税負担等が軽減されるなど労使ともにメリットを享受することができます。
企業型確定拠出型年金(401K)の税制優遇措置
ではここで、企業型確定拠出型年金(401K)の税制優遇措置について復習しようと思います。
- 企業型確定拠出型年金(401K)の税制優遇措置
-
①掛金を拠出しても所得とならないため所得税・住民税は全額非課税となります。
②掛金の運用の結果得た利益には課税されません。
③受取時に退職所得控除、もしくは公的年金等控除を利用できます。
このように、拠出時・運用時・受取時、それぞれに税制優遇を受けれることができます。
もちろん資産運用が原則となる以上、リスクも伴いますが、当社では制度導入に伴い社員の金融リテラシー向上にもつながると考えました。金融知識や税務知識の向上は社員の生活にもメリットをもたらすと考えています。
これらのメリットを踏まえ当社では少人数でも導入可能なSBIみらい年金プランの導入を進めました。
SBIみらい年金プランの特徴
-
加入者1名から導入が可能です。中小企業・小規模企業も導入可能です
人数に関わりなく、加入者1名、役員のみの事業所でも導入可能です。 -
充実した運用商品ラインナップ
インデックス型の運用商品は手数料の低い良質な運用商品が多くあります。 -
規約申請に関する支援、導入のコンサルティングを受けれる
任意加入の選択制の他、要望に応じた制度設計を支援してくれます。
SBIみらい年金プランの導入支援も始めました
特に、規約申請に関する支援や導入後のコンサルティングに関しては専門知識をもつ弊社社員が担当いたします。
制度設計のご相談、導入時の社員向け説明会や、導入後の運用教育についても対応可能です。お気軽にご相談ください。
企業型確定拠出年金(企業DC)の導入支援を行います
「退職金制度がない」「人材が定着しない」「将来の備えをどう整えるべきか分からない」――そんな悩みを抱える経営者の皆さまにとって、企業型DC(確定拠出年金)は有効な選択肢の一つです。
ただ一方で、
「うちのような少人数の会社でも導入できるのか?」
「手続きが煩雑で運用が大変そう…」
「コストや社内への説明が不安だ」
といった声もよく聞かれます。
オンワードマネジメントでは、そうした経営者の視点に立ち、初期段階のご相談から制度設計・導入・従業員説明、さらに運用開始後のサポートまで一貫してお手伝いしています。
貴社にとって「導入して良かった」と実感いただける制度となるよう、伴走型でご支援します。
以下では、導入の具体的なステップと当社のサポート体制についてご紹介します。
導入の流れとサポート
- Step1
- ヒアリング
-
企業の経営方針や従業員の構成、現在の福利厚生制度などを詳しく伺いながら、「なぜ企業型DCを導入したいのか」「どんな形が自社に合うのか」を一緒に整理していきます。まだ方向性が定まっていない段階でも構いません。初期のご相談から丁寧に寄り添い、ご提案いたします。
- Step2
- 制度設計
-
制度をどのように組み立てていくか、会社の実情に合わせて一緒に考えていきます。たとえば、「掛金はいくらにするのか」「どの従業員を対象にするのか」「従来の退職金制度とどう整合性を取るか」など、細かな部分を具体的に設計していきます。制度を導入することで得られる税制の優遇や、社会保険料の見直し効果など、経営面でのメリットについても、数字を使ってわかりやすくお伝えします。
- Step3
- 労使合意・規約作成・申請
-
制度導入にあたっては、労使間での合意や規約の整備が必要です。オンワードマネジメントでは、そのための書類作成や社内説明に必要な資料の準備もお手伝いします。厚生局への申請も代行できるので、手続きが不安な方も安心して進めていただけます。
- Step4
- 社内説明会の実施
-
制度が始まる前に、従業員の皆さんに向けて内容やしくみについて説明会を行います。投資や年金といった聞きなれないテーマもあるため、専門用語を使わず、やさしく丁寧に解説いたします。ご希望があれば個別の相談対応も可能です。
- Step5
- 制度開始・運用スタート
-
制度がスタートした後も、オンワードマネジメントは企業様と従業員の皆さまを継続的にサポートいたします。運用に関するご相談や従業員からの質問対応はもちろん、制度内容の見直しや改定が必要になった際にも、状況に応じて柔軟に対応いたします。
また、ご希望に応じて制度開始後も継続的な投資教育セミナーを実施しています。ライフステージや従業員一人ひとりの理解度に合わせた内容で、金融知識に不安のある方にも安心してご参加いただけるよう工夫しています。
よくあるご質問(FAQ)
-
- Q何人くらいの従業員がいれば導入できますか?
- A小規模企業(10人未満)でも導入実績があります。運用管理機関によって最低人数が異なりますのでご相談ください。
-
- Qどのくらいで制度をスタートできますか?
- A通常、ヒアリングから導入までは約5~6か月程度です。
-
- Q企業型DCの導入にあたり、従業員の同意は必要ですか?
- Aはい、必要です。企業型DCを導入する際には、労使協定を締結し、従業員の同意を得ることが求められます。
-
- Q退職金制度が既にある場合、企業型DCと併用できますか?
- Aはい、可能です。既存の退職金制度を維持しつつ、企業型DCを導入することで、従業員に選択肢を提供することができます。
-
- Q企業型DCの導入後、従業員が退職した場合の手続きはどうなりますか?
- A従業員が退職した場合、その方の企業型DCの資産は、転職先の企業型DCへ移換するか、個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換することが一般的です。
-
- Q説明会や従業員教育もお願いできますか?
- Aはい。専門スタッフによる投資教育や個別相談も可能です。
まずは無料相談で
お気軽にご相談ください
無料相談では、お客様の加入目的やご意向をお伺いして親身に対応いたします。まずは疑問や不安を解消しませんか?
取扱保険会社
損害保険会社
- AIG損害保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- Chubb 損害保険株式会社
- スター保険(スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー)
- 東北自動車共済協同組合
生命保険会社
- メットライフ生命保険株式会社
- 大同生命保険株式会社
- 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
- エヌエヌ生命保険株式会社
- オリックス生命保険株式会社
- ソニー生命保険株式会社
- SOMPOひまわり生命保険株式会社
- 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
- FWD生命保険株式会社
- 富国生命保険相互会社
- メディケア生命保険株式会社
当社は、お客様に適正な選択をいただけるよう、複数の損害保険会社および生命保険会社と代理店委託契約を締結しております。また、上記各社の保険契約の締結の代理または媒介を行います。
保険契約締結における権限について
損害保険( 代理) ・・・募集人が承諾をすればその契約が成立し、その効果が保険会社に帰属することになります。
生命保険( 媒介) ・・・募集人は契約の申込の勧誘のみを行います。契約の成立には保険会社の承諾を必要とします。